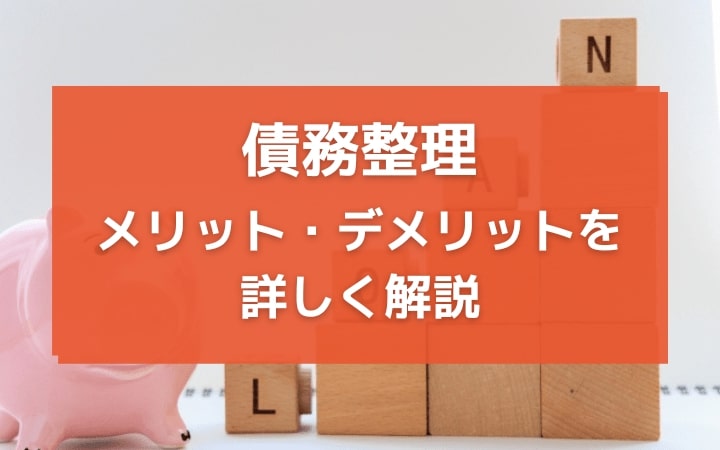
借金問題に苦しむ人は、借金生活から抜け出すためにどのようにしたら良いのか分からない状態の場合が多いでしょう。
債務整理を行うと、何もかもがダメになってしまうというイメージを持たれますが、実際にはそんなことはありません。
生活を立て直す手段として、借金に苦しむ方の生活状況や考え方に応じた方法があるため、検討してみると良いでしょう。
この記事では、債務整理の手続きや、その特徴、メリット・デメリットについてわかりやすく解説していきます。
この記事でわかること
- 債務整理は借金の減額や返済義務の免除ができる
- 債務整理のメリットは5つ
- 債務整理のデメリットはブラックリストに載るおそれがある
- 債務整理は依頼先によって対応範囲が変わる
- 任意整理は利息を免除して分割で返済ができる
- 個人再生は借金を減額できる
- 自己破産は借金を全額免除できる
- 過払い金請求でお金が戻ってくる可能性がある
債務整理は借金の減額や返済義務の免除ができる
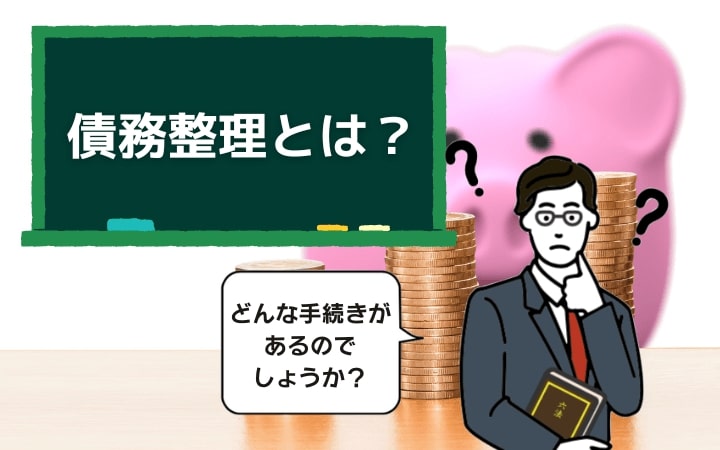
債務整理とは、借金の減額や返済義務の免除が可能な手続きのことで、将来利息の免除といった方法や、払いすぎた利息が帰ってくる可能性があります。
債務整理と聞くと良くないイメージを持ち、手続きを行うのを躊躇ってしまう方が多いのですが、実際はそんなことはなく、生活が改善する可能性が高いです。
それぞれの手続きにメリットとデメリットがあるため、現在の借金状況がより悪化しないように、自分に合った最適な債務整理を選択しましょう。
それでは、債務整理の種類と各手続きの詳細を説明していきます。
債務整理には主に4種類の手続きがある
債務整理には、主に以下の4つの手続きがあり、借金の状況や財産の有無などによって最適な手続きが変わります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 過払い金請求
また、それぞれの手続き毎にメリットとデメリットがあるため、個別に解説していきます。
債務整理のメリットは4つ
債務整理のメリットは、4つあります。
- 返済期間中の利息や遅延損害金を免除できる
- 弁済代行が可能
- 業者からの支払催促が止まる
- 過払い金が発見できる
借金の状況や、財産の有無によっても変わってくるため一概には言えないものの、債務整理の主なメリットはこの4つです。
債務整理を行うと、返済期間中の利息が免除されるため、支払総額の増加するケースはありません。
しかし遅延損害金については免除されない可能性があるため、債権者ごとに確認が必要です。
また、弁護士または司法書士が債権者へ受任通知を行った時点から即支払催促が停止し、債権者からの電話や家へのハガキなど一切が停止します。
弁済代行とは債務者に変わり弁済の代行を行うこと
弁済代行とは、弁護士または司法書士が債務者に変わって弁済の代行を行うことで、以下のようなメリットがあります。
直接のやり取りを行う必要がなくなるため、心身的なストレスからも解放されます。
- 債権者と直接連絡を取らずに済む
- 振り込み回数・金額などの間違いをなくせる
- 借入先が複数あっても振り込みが1回で済む
- 支払えない事情がある場合、すぐに相談できる
債務整理のデメリットはブラックリストに載るおそれがある
すべての債務整理に共通するデメリットとして、ブラックリストに登録される可能性があります。
ブラックリストとは、信用情報機関に債務整理を行った記録(事故情報)が登録されることを指す場合が多く、登録されると一定期間は新たにお金の借り入れや各種ローン、クレジットカードの作成はできなくなります。
ただし、選挙権がなくなる、年金がもらえなくなる、パスポートが取れなくなる、と誤解されますが、そういった事はありません。
債務整理は依頼先によって対応範囲が変わる
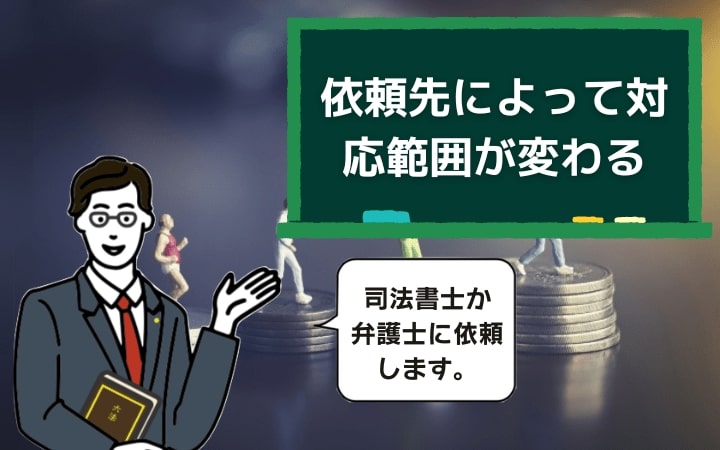
債務整理は誰に依頼するかによって対応可能な範囲が変わります。
依頼先は、司法書士か弁護士のどちらかに限られます。
弁護士は業務に関する制限はなく、賃金業者との交渉から訴訟まで全ての手続きにおいて代理業務を行えます。
それに対し、司法書士は受任通知及び書類準備関係のサポートは可能ですが、その他代理業務に関しては対応できません。
認定司法書士は法律相談、交渉、訴訟などが可能ですが、個別の債権額(借金および過払い金)が140万円以下に限るため、それ以上の債権は代理業務や裁判所への手続きは対応範囲外となります。
弁護士と司法書士の対応範囲の違いを比較
制限のない弁護士のほうが良いわけでは無く、司法書士の業務範囲に制限はあるものの、依頼者に寄り添った対応という点については弁護士とそれほど差はありません。
また、債務整理は専門家に依頼せずに自分でも手続きは可能ですが、書類作成から債権者への対応も全て自分で行うことになります。
受任通知も無く、取り立てや返済が続く為、知識と精神力がある方以外はおすすめできません。
以下、それぞれの対応範囲を一覧にまとめています。
| 項目 | 弁護士 | 司法書士 | 自分 |
|---|---|---|---|
| 受任通知 | 〇 | 〇 | × |
| 書類準備 | 〇 | 〇 | △ |
| 申し立て | 〇 | × | △ |
| 裁判所への同行 | 〇 | × | – |
| 個別の債権額が140万超え法律相談、交渉、訴訟 | 〇 | × | △ |
| 個別の債権額140万以下法律相談、交渉、訴訟 | 〇 | △認定司法書士のみ | △ |
任意整理は利息を免除して分割で返済ができる
任意整理とは債務整理の中では最も簡易的な方法で、お金を借りている債務者がお金を貸してくれている債権者と交渉を行い、月々の返済額や利息の軽減などのために交渉を行って和解するための手続きのことです。
債権者との直接交渉のため、裁判所への手続きが不要で費用も最も定額なうえ、周囲にバレる可能性も低いです。
さらに、将来利息負担が免除され、月々の返済を減額されますが、借金の額が大きい方は月々の返済額はそれほど下がらない場合があります。
信用情報機関へ事故情報が約5年間記録されるため、その間は新たな借入はできません。
任意整理は制限や条件が少ない
任意整理は自己破産や個人再生に比べて制限は少ない手続きで、 任意整理しても資格制限や職業制限は生じません。
したがって、自己破産では資格制限がある職種であったとしても、任意整理では問題なく続けられます。
任意整理は財産を失わずに借金返済額を減らせるうえ、どの借金を減らすのか債務者が選べるのも特徴で、任意整理しない方が良い、またはしたくない借金を区別できます。
任意整理は一定の収入がないと厳しい
制限や条件が少ない任意整理ですが、3〜5年分割で返済をしていくことを踏まえると、最低限は返済が困難にならない程度の収入は必要になります。
多重債務者や借入総額が大きい方は、任意整理を行っても月々の返済額はあまり減らない可能性が高いです。
そのうえ、個人再生や自己破産の方が適切である場合もあるため、まずは借金の状況を相談しましょう。
たとえば150万円の借金を任意整理し、3年の分割返済をしたと仮定すると「月4〜5万円」の返済が必要となります。
個人再生は借金を減額できる
裁判所を対象に借金減額を申し立て、借金総額を1/3〜1/5まで減額し、3年〜5年かけて分割で返済していく手法です。
自己破産とは異なり、家や財産を手放さずに手続きが可能で、特定の職業に就けないといった資格制限などを受けることもありません。
ただし、個人再生の主なデメリットとして、借金を全額免除できない点や整理する対象を選べないないことが挙げられます。
つまり、 自己破産のようにすべての借金を免除してもらえず、任意整理のように整理する対象を選べず、全ての債権者に対して平等に手続きを行います。
裁判所を通しての手続きのため、借金を隠してこの人にはこっそり返済しようと考えていても、それが発覚して債務整理自体ができなくなる危険性があります。
それにより信用情報期間へ事故情報が約5年間記録され、その間は新たな借入はできません。
収入と借金総額に応じて手法が変わる
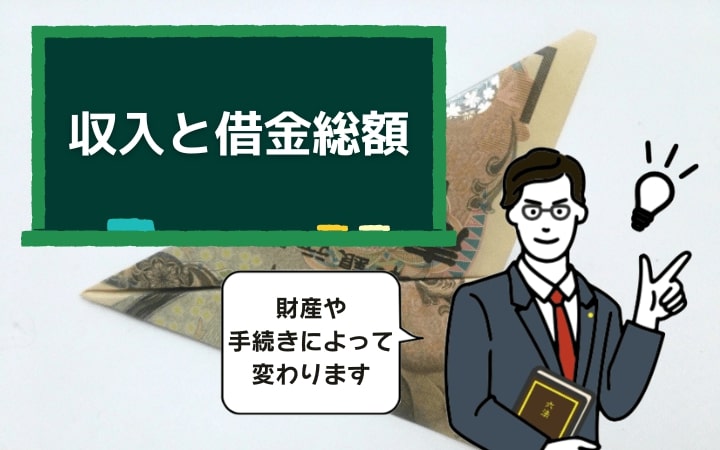
下記3項目があり、どれが適用されるかは財産の保有状況や手続きの種類次第となります。
- 最低弁済基準額
- 清算価値保障基準
- 可処分所得基準
最低弁済基準額は、民事再生法で定められた最低弁済額の基準です。
ただし、個人再生の主なデメリットとして、借金を全額免除できない点や整理する対象を選べないないことが挙げられます。
三 前号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円を超え五千万円以下の場合においては、当該無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第八十四条第二項各号に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が当該無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の十分の一を下回っているとき。
四 第二号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円以下の場合においては、計画弁済総額が基準債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額(基準債権の総額が百万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは三百万円)を下回っているとき。
民事再生法 第231条
では、詳しい内容を分かりやすく解説していきます。
小規模個人再生は借金の総額5,000万円以下
小規模個人再生とは、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であり、なおかつ将来にわたって継続的に収入を得る見込みがある人を対象とした手続きのことをいいます。
主に、個人で商店を経営している、小規模事業を営んでいる人などを対象としたものです。
原則として3年間で、最低弁済額もしくは保有財産の合計金額いずれか多いほうの金額を最低限返済します。
※借金総額 最低弁済額とは
| 100万円未満 | 全額 |
|---|---|
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円以上5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
また、以下の条件を満たさないと再生計画が認められません。
- 債権者合計の2分の1以上の反対がない
- 反対した債権者の、債権合計額が全債権額の1/2を超えない
つまり全債権額1000万円なら、反対した債権合計額が1/2である500万を越えなければ条件を満たします。
給与所得者等再生は継続した収入があるひとが該当
給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる人のうち、主にサラリーマンの方や安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用する手続きのことをいいます。
最低弁済額のほか、可処分所得といった収入から所得税などを控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額の2年分のうち、いずれか多い方の金額を最低限返済していきます。
一般的には小規模個人再生よりも返済額が高額になりますが、先述した再生計画の条件はありません。
自己破産は借金を全額免除できる
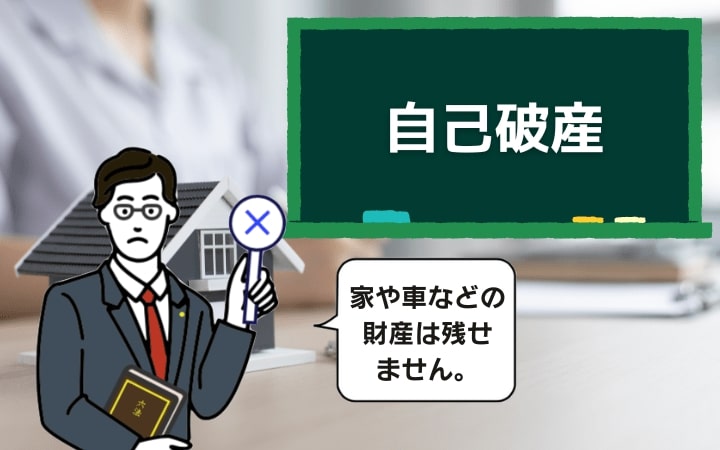
自己破産とは、多重債務等により借金が膨らみすぎて支払不能となった個人に対し、裁判所を通して申し立てを行ない、借金全額を免責してもらう手続きのことです。
原則として全ての借金を支払う義務はなくなりますが、持ち家や自動車などの財産価値があるものは一切残せません。
しかし、生活に不可欠な財産は処分されないため、生活に支障がでることはありません。
債務整理の中では最終手段に位置する手続きで、信用情報機関へ事故情報が約10年間記録されるため、その期間は新たな借入はできません。
財産がない場合は同時廃止事件
自己破産の手続きには同時廃止事件と管財事件があり、債権者に分配するほどの財産を保有していない場合は、同時廃止事件になります。
破産手続きの開始と同時に破産事件が廃止されるため「同時廃止」と言います。
目安としては、20万円以下であれば財産が無いに等しく、車でも新車購入から5年以上経過してからは売却しても20万円以下になるケースがほとんどです。
財産や免責不許可事由に該当する場合は管財事件
一定以上の財産がある、もしくはギャンブルでの借金など自己破産に至った経緯に問題が多い場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。
該当した場合は、財産がなくても同時廃止事件は選べず、管財事件となります。
つまり、管財事件となると破産管財人による財産の調査・換金・債権者への分配が行われ、破産管財人へ予納金を納める必要があるため、同時廃止事件と比べて時間も費用も掛かることとなります。
免責不許可事由に当てはまるかは確認することが重要になります。
予納金が少額になる少額管財事件
少額管財事件とは、管財事件における負担の軽減を目的としており、手続きが簡略化され期間が短くなり、さらに予納金が少額になる手続きのことです。
一部の裁判所だけしか用いられておらず、弁護士に依頼していること、債権者数が多くなく借金状態が複雑ではない等の条件があります。
資格や職業が制限される
破産手続き中は、一定の職業や資格が停止されます。
制限職種で一時的な配置転換、休業等も期待できない場合には、個人再生を検討するのも良いでしょう。
| 資格 | 制限法令 |
|---|---|
| 弁護士 | 弁護士法7条の5 |
| 弁理士 | 弁理士法第8条10 |
| 司法修習生 | 司法修習生に関する規則17条1の3 |
| 司法書士 | 司法書士法第5条3 |
| 土地家屋調査士 | 土地家屋調査士法第5条3 |
| 不動産鑑定士、不動産鑑定士補 | 不動産の鑑定評価に関する法律第16条3 |
| 公認会計士、公認会計士補 | 公認会計士法第4条5 |
| 税理士 | 税理士法第4条3 |
| 社会保険労務士 | 社会保険労務士法第5条3 |
| 行政書士 | 行政書士法第2条の2 |
| 中小企業診断士 | 中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第5条3 |
| 通関士 | 通関業法第31条2 |
| 外国法事務弁護士 | 外国法事務弁護士記章規則第6条5 |
| 宅地建物取引士 | 宅地建物取引業法第18条3 |
| 宅地建物取引業 | 宅地建物取引業法第5条 |
| 管理業務主任者 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条1 |
| マンション管理業 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条1 |
| 旅行業務取扱管理者 | 旅行業法第11条の2の2 |
| 公証人 | 公証人法第14条2 |
| 人事院の人事官 | 国家公務員法第5条3、第8条1 |
| 市町村農業委員会の委員 | 農業委員会等に関する法律第8条4の1 |
| 漁船保険組合の組合員 | 漁船損害等補償法第24条4 |
| 生命保険募集人及び損害保険代理店とその役員 | 保険業法第279条、280条 |
| 警備員 | 警備業法第14条 |
| 警備業者 | 警備業法第3条1 |
| 一般建設業、特定建設業 | 建設業法第8条、第17条 |
| 建築設備資格者 | 建築設備資格者登録規定第6条 |
| 測量業者 | 測量法第55条の6 |
| 土地鑑定委員 | 地価公示法第15条 |
| 地質調査業者 | 地質調査業者登録規定第6 |
| 有位者 | 位階令第6条 |
過払い金請求でお金が戻ってくる可能性がある
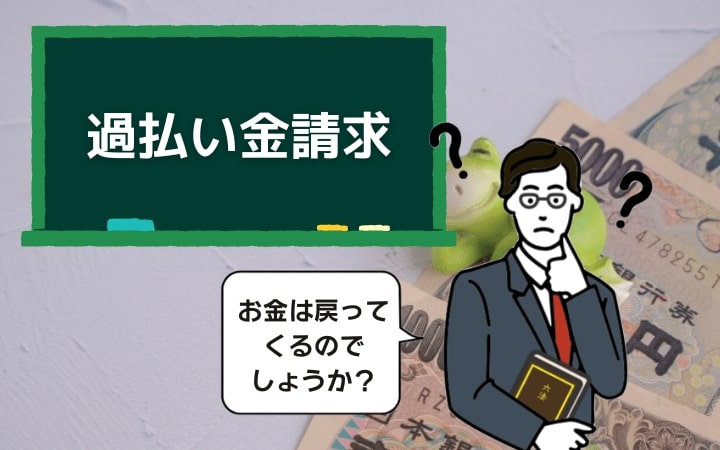
過払い金請求とは、これまでに払い過ぎた金利を貸金業者に請求して、返還してもらう手続きのことです。
返還されたお金で借金がなくなる可能性もあり、メリットが大きい手続きです。
しかし、借金を完済せずに行うと、信用情報機関へ事故情報として登録されてしまうデメリットがあります。
過払い金請求にかかる費用の相場は10万円程度で、過払い金が取り戻せれば成功報酬が発生します。
和解で過払い金を取り戻した場合は20%、裁判の場合は25%が成功報酬の上限になっています。
ただし、過払い金請求を行う前に、過払い金があるかを確認しましょう。
自分が対象か確認が必要
借金返済中に過払い金請求をすると、過払い金が無かった場合でもブラックリストに登録されるリスクがあります。
そのため、自分が対象になるのか確認しましょう。
過払い金請求の対象者は次の3つの条件を満たす人です。
- 2010(平成22)年6月17日以前に借入を開始した人
- 年20.0%以上の金利で借りた人
- 借金を返済中、または完済から10年以内の人
過払い金は、最後に借入・返済をした日から10年が経過すると時効で消滅してしまうため、早めに確認することが大事です。
各債務整理の違いを一覧で確認
| 種類 | 内容 | 所要期間と費用 | 手順 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 債務整理の中では最も簡易的な方法で、お金を借りている債務者が、お金を貸してくれている債権者と交渉を行い、月々の返済額や利息の軽減などのために交渉を行って和解するための手続き | (期間)2~4ケ月但し、過払金の回収が含まれる場合には、6~12ケ月程度となる場合もある (費用)債権者1社につき2万円~4 万円これに報酬(減額または過払額の1~2 割)が加算 | ①面談 ②債務整理の依頼 ③受任通知の送付 ④引き直し計算 ⑤返済条件の協議 ⑥返済計画の合意 ⑦⑥に基づき返済 |
| 個人再生 | 裁判所を対象に借金減額を申し立て、借金総額を1/3~1/5まで減額し、3年~5年かけて分割で返済していく手続き | (期間)半年程度 (費用)30 万円~60 万円程度 | ①面談 ②債務整理の依頼 ③受任通知の送付 ④申立 ⑤借金額の確定 ⑥再生計画案の提出 ⑦⑥につき意見聴取、決議 |
| 自己破産 | 多重債務等により借金が膨らみすぎてしまい支払不能となった個人に対し、裁判所を通して申し立てを行ない、借金全額を免責してもらう手続き | (期間)2ケ月~半年程度 (費用)25 万円~55 万円程度(但し、別途予納金を納める必要あり、同時廃止事件(管財人が付かない場合)には1万円程度、管財事件(管財人が付く場合)には20~30万円程度) | ①面談 ②債務整理の依頼 ③受任通知の送付 ④破産手続き開始免責許可の申立財産の売却、代金分配 ⑤破産手続き終了免責許可決定 |
債務整理によくある疑問はこの3つ
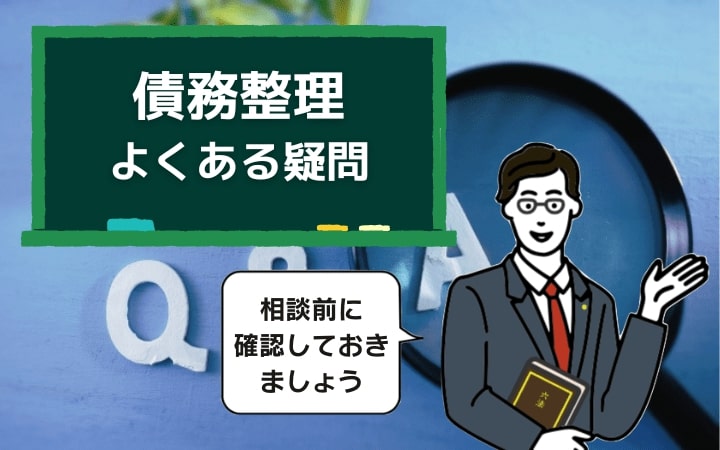
債務整理に良くある疑問は、以下の3つがあげられます。
- 生活保護受給者の手段 自己破産のみ
- 代理での申し立ては原則不可
- 債務整理は家族には影響が出ない
債務整理をする方で、債務整理のメリット・デメリットは分かったけど、こういった状況の時はどうなるのかといった疑問を多く持たれることも多いでしょう。
疑問の多くは、弁護士や司法書士に相談する際に確認をして解決する場合が多いのですが、相談する前に知っておきたい疑問もあるかと思います。
良くある疑問についての回答をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
生活保護受給者の手段 自己破産のみ
債務整理には、自己破産のほかに個人再生と任意整理があります。
しかし、個人再生は将来にわたって継続して安定した収入を得られることを前提にしているので、生活保護受給者は利用できません。
また、任意整理で分割返済を行う場合においても、生活保護法が目的とする最低限度の生活さえできなくなってしまうので、任意整理も行えません。
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
生活保護法 第一条
代理での申し立ては原則不可
債務整理は、たとえ家族だとしても本人の代理での申し立ては原則不可です。
借金は本人が金融業者と交わした契約関係に基づくものであり、その契約内容を当事者以外の者が債務整理によって変更できないのが理由となります。
債務整理は家族には影響が出ない
債務整理の効果は、本人のみに効果があり、家族であっても本人以外の第三者には一切影響しない為、法律上は本人以外の家族の方の財産が処分されたり、進学・就職に障害になることはありません。
ただし、家族の方が保証人になっている場合には、代わりに返済しなければならない為、影響が生じてしまいます。
まとめ
債務整理を検討しているが、どういった手続きがあるのか、なにから始めたら良いのか、メリットからデメリットまでをみてきました。
借金問題は慌てて対応すると状況を悪化させてしまう可能性があり、慎重になってしまいがちですが、まずは債務整理を検討して相談してみてはいかがでしょうか。
この記事を参考に、ぜひ借金問題を良い方向に進めてみてください。
